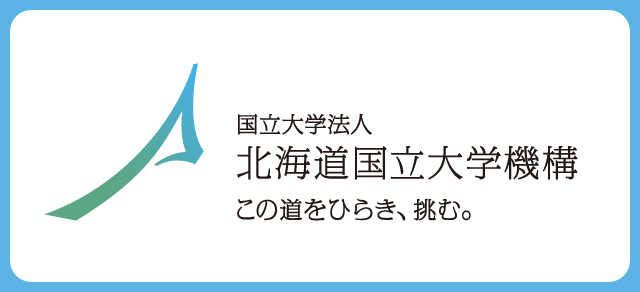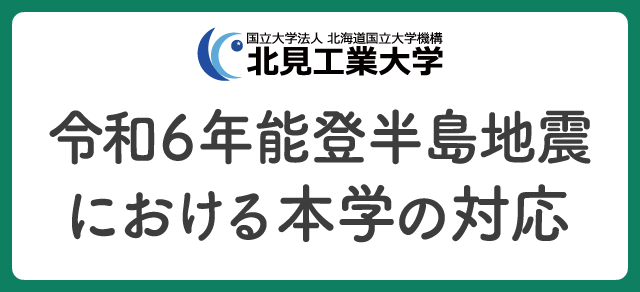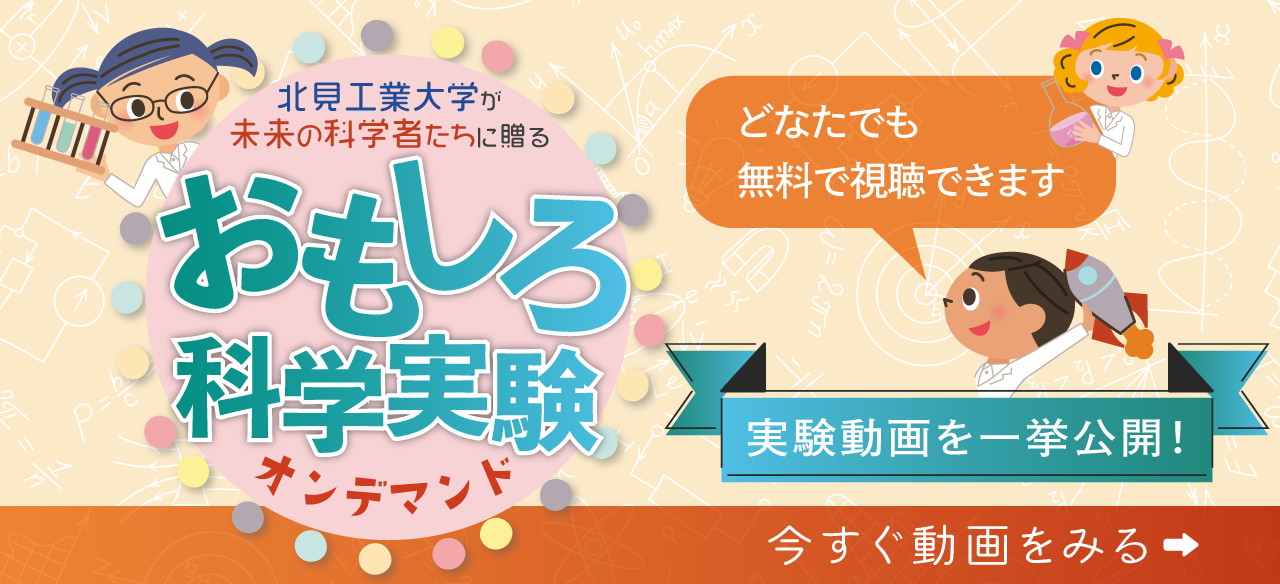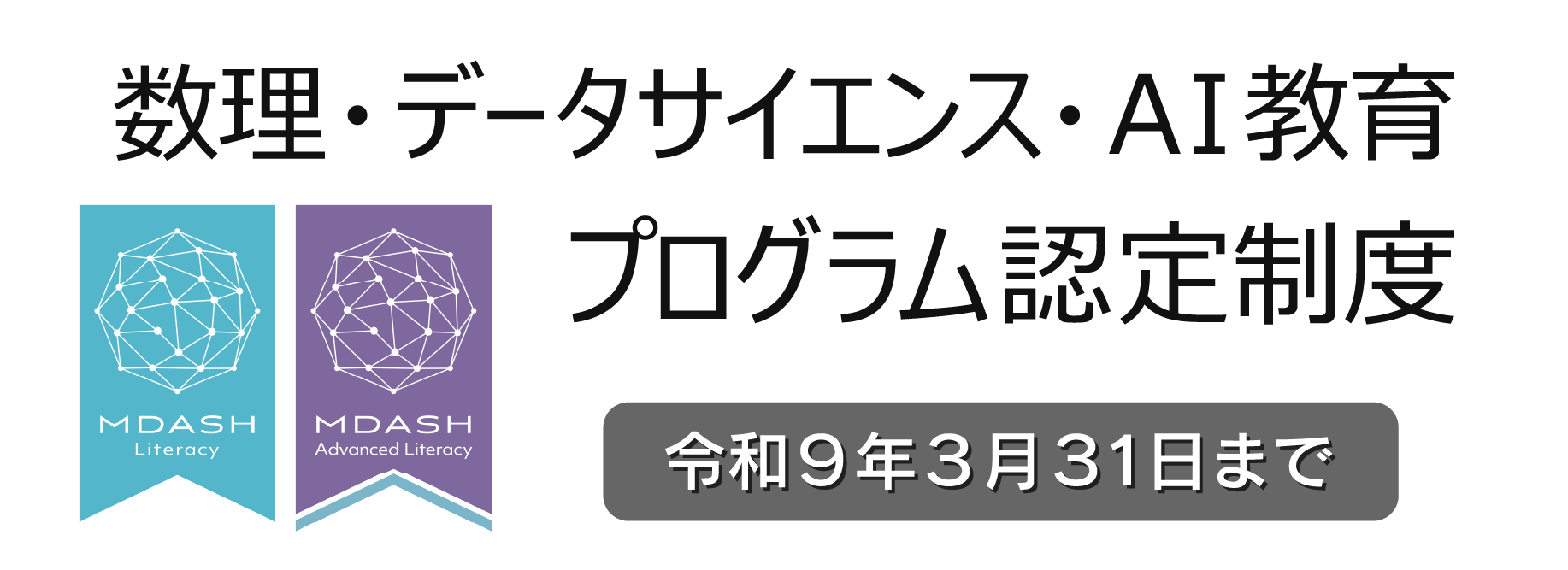NEWS
-
名誉教授を更新しました
名誉教授のページを更新しました。詳しくはこちらをご覧ください。
-
令和6年度一般選抜(後期日程)個別学力検査における入試ミス(採点ミス)について
令和6年3月12日(火)に実施しました、令和6年度一般選抜(後期日程)個別学力検査の「理科(物理)」において、入試ミス(採点ミス)があったことが判明しました。これを受け採点をやり直し、改めて合否判定を行った結果、新たに2名の受験生を合格といたしました。 厳正、確実であるべき入学者選抜においてこのような事態を引き起こし、受験生の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深
-
編入学学生募集要項を公表しました
令和7(2025)年度編入学学生募集要項を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
-
入学者選抜における変更点を更新しました
入学者選抜における変更点を更新しました。詳細は、入学者選抜における変更点をご覧ください。
-
2024新入生交流会を開催しました
4月8日(月)午前10時から、令和6年度新入生を対象とした「2024新入生交流会」を開催しました。本イベントは、今回が初めての開催で、大学で勉強以外にどんな経験ができるのかを知ってもらい、クラス単位の交流だけでなく、色々なネットワークを構築してほしいという思いから企画したものです。 交流会は2部構成で行われ、第1部では、本学多目的講義室において、女子学生を対象とした交流会を実施しました。 川村み
-
本学教員の結核診断について(第1報)
令和6年3月4日、本学教員1名が肺結核の診断となりましたので、お知らせいたします。本診断は、定期健康診断において発見された異常をもとに精密検査を行った結果、症状がでる前の段階で発見に至ったものです。そのため、第三者への感染の危険は低い状態と考えられます。診断後、保健所と協力しつつ学内にて進めた疫学調査においても、現時点で他に感染者は確認されていません。 結核は、咳を通じて菌が体外に拡散する疾患で
-
学長告辞を公開しました
令和6年度入学式 告辞(2024年4月5日)を公開しました。詳細は、告辞・挨拶等をご覧ください。
-
【3/29更新】令和6年度入学式のご案内
【2024/3/29更新】 入学式前後の大学行事予定について追記しました。令和6年度入学式のご案内令和6年度入学式を下記のとおり挙行します。 記 ○ 日 時 令和6年4月5日(金) 午前10時 (開場:午前9時15分予定)○ 場 所 北見市民会館 大ホール (北見市常盤町2-1-10) 保護者の方も式典にご参加いただけます。(人数等の制限はございません。) 式典の様子は、イ
-
(3/29更新)【令和6年度学部・大学院ご入学の皆様へ】新入生ガイダンスのご案内
【2024/3/29更新】 ●新入生全体ガイダンス(1日目)について追記しました。 ●「令和6年度学部新入生ガイダンス日程表」を更新しました。 ※新入生配付物受取場所については、ガイダンス当日に決定したものをお配りします。令和6年度入学式前後の4月4日(木)~5日(金)、新入生ガイダンスを行います。学部生と大学院生では日程等が違いますので、詳細は下記をご確認ください。地球環境工学科・地域未来デザ
-
本学大学院生が表面技術協会第149回講演大会において学術奨励講演賞を受賞
3月5日(火)~6日(水)、工学院大学(東京都)において開催された、一般社団法人表面技術協会第149回講演大会において、本学大学院生の飯野寛海さん(博士前期課程 工学専攻 応用化学プログラム1年、指導教員:川村みどり教授)がポスター発表を行い、学術奨励講演賞を受賞しました。 飯野さんの受賞題目は、「低温基板上へのスパッタ成膜におけるスパッタガス種の影響」です。卒業研究から、液体窒素で冷却した基板