北海道産食素材の生理活性評価と高度利用法の研究開発
- 研究キーワード
-
- 機能性食品
- ポリフェノール
- アレルギー緩和
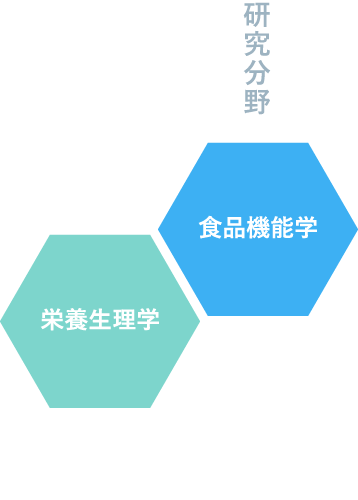
近年、生理機能を示す食品が注目されており、さまざまな特定保健用食品や機能性表示食品が開発されています。オホーツク地域に特有の農産物(ハマナス、タマネギ、ハッカ等)に含まれるポリフェノールをはじめとする抗酸化物質の生理活性(抗アレルギー、抗炎症、抗動脈硬化症)を培養細胞を用いて評価し、地域の産業・経済の振興に貢献します。
食品由来ポリフェノールによる
抗アレルギーおよび抗炎症作用
国民のアレルギー疾患の罹患率は現在約50%であり、さらに増加傾向にあります。花粉症等のアレルゲンの体内侵入は、免疫細胞である好塩基球等を刺激し、ケミカルメディエーターによる過剰な粘液分泌等の症状を呈します。細菌・ウイルス感染などによる局所的組織障害は、免疫細胞であるマクロファージ等を刺激し、一酸化窒素およびサイトカインによる炎症反応を誘導します。
アレルギーや炎症の抑制は、薬剤に依存していますが、副作用が懸念されています。食品の生理機能の一つとして、アレルギーや炎症を抑える作用をもつ食品成分を探索し、そのメカニズムを解明しようとしています。特に植物由来のポリフェノールに注目し、培養細胞から放出されるヒスタミンを測定することによって、アレルギー抑制効果を評価しています。ハマナスは北海道の海岸に多く自生するバラ科植物であり、花弁は主にハーブティーや化粧品等に利用されています。ハマナス等に含まれる食品由来ポリフェノールの抗アレルギーおよび抗炎症作用を培養細胞を用いて明らかにしています。


他にも、北海道でも近年栽培されており、ユーラシア大陸中北部に広く分布するシーベリーという落葉低木に注目しています。シーベリーの果実には、抗酸化作用、抗腫瘍作用等を示す成分が含まれています。また、キバナオウギという北海道でも栽培されているマメ科多年草に含まれる抗炎症作用に着目し、アレルギー抑制効果について調査・解析を行っています。
食品由来抗酸化物質による
アテローム性動脈硬化症の予防
脳血管疾患および心血管疾患などの循環器系疾患は、日本人の死因の約1/4を占め、その予防は国民の健康を維持する上で重要な課題です。脳血管疾患および心血管疾患の主な原因であるアテローム性動脈硬化症は、活性酸素(ROS)による低密度リポタンパク質の(LDL)の酸化によって誘導されます。
LDLの酸化を抑制する食品成分を探索し、アテローム性動脈硬化症を予防する機能性食品の開発に貢献します。
PERSONAL DATA
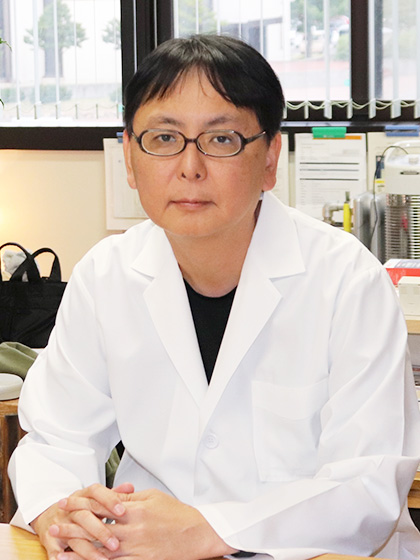
新井 博文Hirofumi Arai
応用化学系 教授
- 専門分野
- 食品機能学、栄養生理学
- 所属学会
- 日本フードファクター学会、日本食品科学工学会、日本栄養・食糧学会、日本農芸化学会、日本酸化ストレス学会
- 担当授業科目(学部)
- 食品機能学、食品栄養生理学、食品化学、基礎生物学
- 担当授業科目(大学院)
- 生命科学特論Ⅰ、食品工学特論
- 主な研究テーマ
- 培養細胞を用いた食品成分のアレルギー抑制作用評価
- 研究キーワード
- 機能性食品、ポリフェノール、アレルギー緩和、生活習慣病予防
