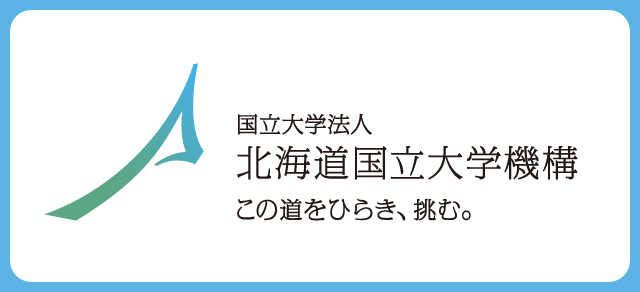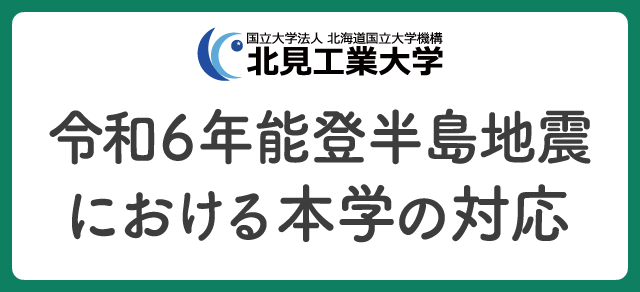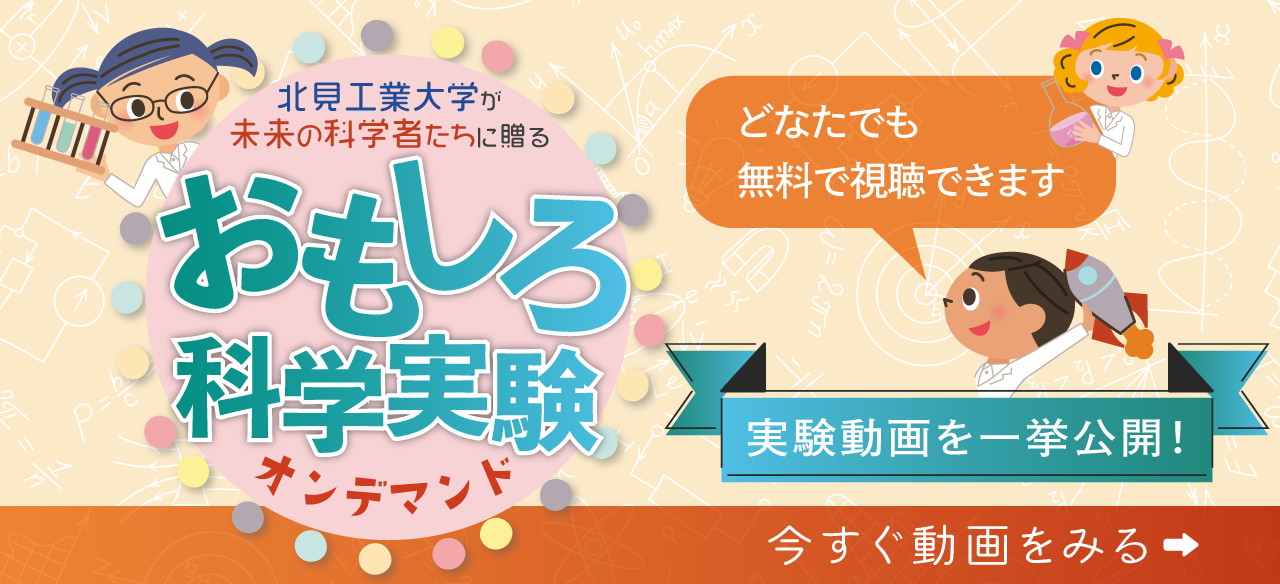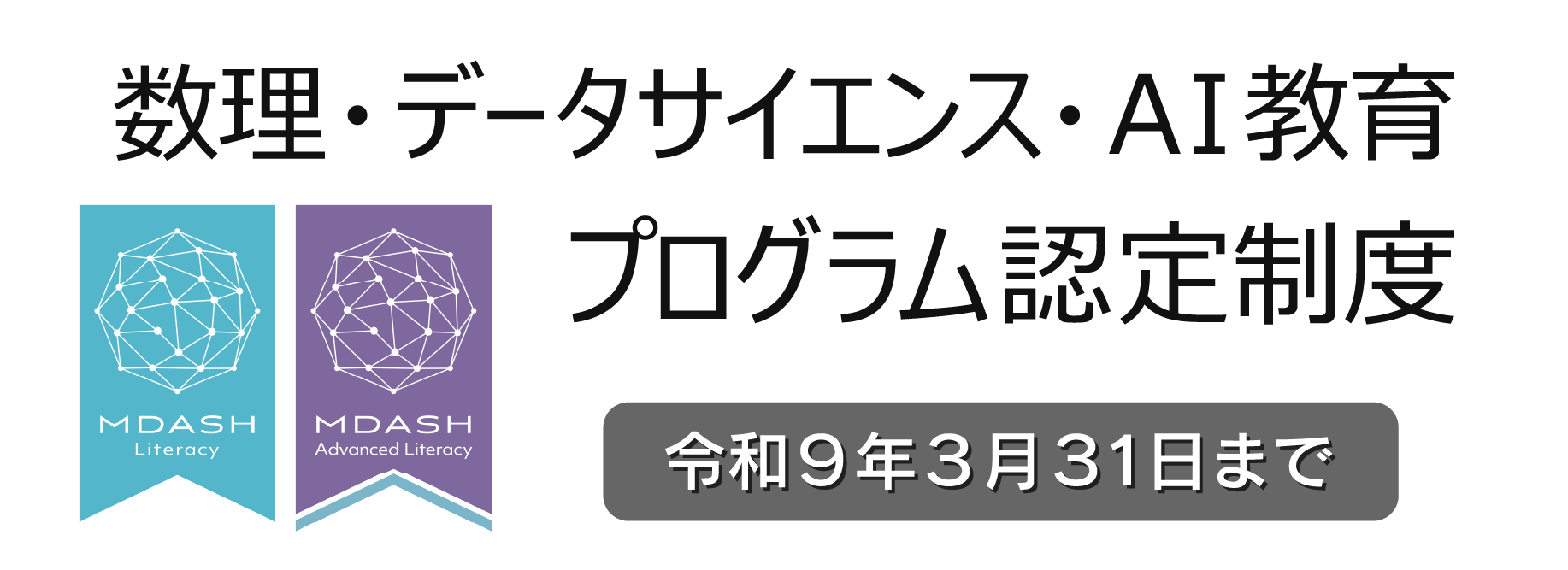NEWS
-
令和6年度保護者懇談会(春季)開催のご案内
令和6年度春季の保護者懇談会は、6月8日(土)にオンラインで開催し、6月22日(土)に対面にて開催します。保護者懇談会では、ご子女の修学状況等について個別担任と面談していただきます。これまで保護者懇談会の会場が遠方のため参加が難しかった保護者の皆様も、この機会にぜひご参加ください。参加申込方法詳細や参加申込については、保護者懇談会特設ページをご覧ください。[申込締切:5月12日(日)]※締切厳守(
-
物品等の入札情報を更新しました
物品等の入札情報を更新しました。詳細は、物品等の入札情報のページからご覧ください。
-
令和6年度オープンキャンパス(全3回)を開催します
令和6年度オープンキャンパスは、以下のとおり全3回開催します。お申し込み等、詳細については決まり次第、本ページにて随時お知らせします。実際に本学にお越しいただき、様々な体験を通してその魅力を肌で感じていただける貴重な機会ですので、多数のみなさまのお越しをお待ちしています。令和6年度オープンキャンパス開催概要開催日程(全3回)回 数日 時申込期間第1回6月23日(日)※大学祭と同時開催09:30~1
-
本学教員2名が公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団の学術研究助成に採択されました
このたび、地域未来デザイン工学科の兼清泰正准教授とフォン チャオフイ助教が、公益財団法人 飯島藤十郎記念食品科学振興財団による2023年度学術研究助成(個人研究)にそれぞれ採択され、4月19日(金)に山崎製パン総合クリエイションセンター(千葉県)で開催された贈呈式において、研究助成金が授与されました。 本財団の学術研究助成事業は、米麦その他の主要食糧等を原料とする食品の生産・加工・流通並びに食品
-
北海道国立大学機構シンポジウム「北海道から切りひらく日本の未来~食・エネルギー・防災を支えるデジタル空間~/北海道国立大学機構の挑戦」を開催します
5月23日(木)、日経カンファレンスルーム(東京都)において、北海道国立大学機構シンポジウム「北海道から切りひらく日本の未来~食・エネルギー・防災を支えるデジタル空間~/北海道国立大学機構の挑戦」を開催します。 本シンポジウムでは、三大学の取り組みの一部をご紹介するとともに、多彩なゲストによる議論を通じて北海道の発展に貢献する北海道国立大学機構の将来像を模索します。 開催はハイブリット形式で行い
-
学長メッセージを公開しました
榮坂俊雄学長のメッセージ(2024年4月)を公開しました。詳細は、学長メッセージをご覧ください。
-
名誉教授を更新しました
名誉教授のページを更新しました。詳しくはこちらをご覧ください。
-
令和6年度一般選抜(後期日程)個別学力検査における入試ミス(採点ミス)について
令和6年3月12日(火)に実施しました、令和6年度一般選抜(後期日程)個別学力検査の「理科(物理)」において、入試ミス(採点ミス)があったことが判明しました。これを受け採点をやり直し、改めて合否判定を行った結果、新たに2名の受験生を合格といたしました。 厳正、確実であるべき入学者選抜においてこのような事態を引き起こし、受験生の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深
-
編入学学生募集要項を公表しました
令和7(2025)年度編入学学生募集要項を公表しました。詳しくはこちらをご覧ください。
-
入学者選抜における変更点を更新しました
入学者選抜における変更点を更新しました。詳細は、入学者選抜における変更点をご覧ください。